1週間前にTopping D90が我が家のデバイスに加わりました。
で、この1週間で2回の改造を加えました。
Topping D90のケツを叩く・其の一
Topping D90のケツを叩く・其の二
笑っていただけたら幸いです。
我が家の愛機
1週間前にTopping D90が我が家のデバイスに加わりました。
で、この1週間で2回の改造を加えました。
笑っていただけたら幸いです。
@ジャイアン さん、今回は愛器という範疇から離れていると思いますが、ラズパイをスピーカーの振動を受けにくいようにフローティングさせてみました。プラシーボかもしれませんが、アナログ機器やレコードプレーヤーのようにラズパイというデジタルの塊でも影響が多少なりともあるのかな?と思い始めています。
具体的には、ラズパイを柔らかめのアース線を切って足にして浮かせてみました。こういうお遊びも面白いかもしれませんね(^^♪
@hiroget9 さん
ここは自分の愛機に関わることなら何でもござれの場です。こうした内容も大歓迎ですよ!
振動の影響はよく語られるテーマですね。我が家の環境では、微細な振動以前に色々と問題だらけで、とても振動の影響にまで気が回りません。そもそも私の耳で聴き分けられるのか?という疑問があります(笑)
@ジャイアン さん
経験上、DACは振動の影響を受けやすいように思います。
梱包材のプチプチありますよね。
あれを数回折り畳んで十分な厚みを持たせてDACの下に敷いてインシュレータ代わりに使ってみてください。2〜3㎝の厚みは必要です。
これで音質改善が見られるようなら、DACの設置方法を工夫することによって音質改善の余地があるということが分かります。
なお、プチプチは重量物を支えると徐々に空気が抜けてしまうので、長期間の使用には耐えません。それでも最初の数週間は素晴らしいフローティング性能を発揮してくれます。手軽なのにすごく効果があって面白いですよ!
@パパリウス さん
私の駄耳でどこまで聴き取れるか分かりませんが、DACの下に梱包用の緩衝材をひいてみました。プチプチがなかったので、代わりにシート状のモノを何回も折り重ねて3cm程にして試しています。こんなモノでも効果があればラッキーなのですが、問題は私の耳で効果を感じ取れるかです(汗)
かなり昔のことになりますが、別府俊幸氏設計のフィリップスのTDA1451Aを使った4パラ・モノラル仕様の自作基板の1枚を、再生中に4本のネジサポートから外したことがあります。寸法精度が悪い自作機なので、引き抜く時に何本かのネジと基板がこす、ザリザリというような大きな音が出ました。DACチップは震動に弱く、それが再生音に反映されるということを体験しました。
震動防止のためDACチップの上に重りを貼り付けるという対処法を別府氏が推奨していましたが、今のラズパイシステムでも手で持ち上げると音が変わります。ハハリウスさんのプチプチ方法の他、レコードプレヤーの振動対策も参考になるかも知れません。
@kochan さん
なるほど、DACチップの上に重りですか。
確かにそれは効きそうです!すぐに試してみます。
他にも振動に弱そうな部品はありますでしょうか?
振動によって特性が変わったり電流が生じるような部品があれば、重りをつけてみたいです。
@ジャイアン さん
空気層がバネとして、また空気の振動を絶縁する層として機能するのがポイントなんだと思います。
そのうちプチプチを入手する機会もあると思うので、ぜひお試しください。
もし効果を感じて興味をお持ちになったなら、振動対策のノウハウも共有しましょう!
フローティングだけでは効果が弱く、振動を外に逃す工夫と併用するのがポイントになります。
DACだけではなく、スピーカーの振動対策も面白いです。効果が大きいです。こちらも、フローティングして床から切り離すことと、キャビネットの振動のエネルギーを素早く外部に逃す工夫の併用がポイントです。
拙宅のスピーカーはキャビネットの鳴きも音作りに生かすような古い設計思想のスピーカーなんですが、鳴きを素早く収束させると、響きの美しさを失わずにより現代的な空間表現を見せてくれるようになりました。
みなさん こんにちは
最近のマイブーム(廻りの人たちも含めて)は、何でも吊るすことです。
アンプの振動対策のような話をしていた時、アンプを吊ってみたらどうなるんだろうといった流れになり実際に吊るしてみたのです。
激変です。一口で言うと音がパラパラとほぐれた状態で出てくるようになります。真空管アンプを吊った方もいますが、大変喜んでおりました。
そこでDACやその他のものも吊ってみましたが、同じような傾向の変化があります。
RasPi+Hat-DACについては、小さな取っ手付きのかごを吊るしてその中に入れたり、紙紐で軽く縛ったものを吊るして使っていますが、なかなか良いですね。
DACに関しては、AK4495の音質確認用に買った安い中華製のがずっと常用になっています。その後、作りの良いAK4495基板や、別のチップを使った基板を使い組み立てましたが、結局最初のやつばかり使っています。実はこの基板だけDACチップにφ15✕15ぐらいの銅の塊を気まぐれで接着していました。もしかするとずっと使い続けている原因がこの銅の塊にあるのかもしれません。
@moct さん
kochanさんに教えてもらったDACチップの重り、さっそくやってみましたが予感した通りの、とても良い感触です。
moctさんのように丁度良いサイズの銅片を注文して載せてみようと思います。
一点教えて欲しいのですが、どのような方法で重りを接着なさってらっしゃいますか?
私はとりあえず、両面テープを使ってみました。
DACチップ-両面テープ-ファインメットシート-両面テープ-真鍮製の重り
という感じです。
銅片を入手したら、改めてきっちりとくっつけてみようと思っています。
アンプの吊り下げについても、チャレンジしてみようと思います。(お盆休みの楽しみに取っておきます )
)
@パパリウス さん
>どのような方法で重りを接着なさってらっしゃいますか?
エポキシ系の接着剤(2液性)です。
テストの場合はアセトンで剥がせる普通の瞬間接着材でも良いと思いますが、絶対剥がさないと覚悟を決めたなら?DACチップのモールド素材に近いエポキシ系の接着剤が良いと思います。
我が家に新しいスピーカーが仲間入りしました。
@ジャイアン さん、エッジの張替えご自分でされるとは恐れ入りました。私ならオーディオ店に持ち込んでいることでしょう。
話は変わりますが、ラズパイにアース線付けてみました。
プラシーボだと思うのですが、音がすっきりりしたような気がします。気のせいでしょうね(^^♪
@hiroget9 さん
私のブログにご訪問いただけたようで感謝です。
スピーカーエッジの貼り替えは特別難しいことはなくて、パーツと道具を全部揃えて、焦らず粛々と作業を進めるだけなんです。特別なコツもありません。私自身も、エッジの貼り替えは人生二度目。ましてや、今回のようにユニットを取り外すだけでも大仕事となるケースは初めて。なので困難さを楽しむという姿勢でのぞみました。失敗したらしたで、それもまたいい経験になりますでしょうし。
エッジは必ず劣化する部分なので、スピーカーの長期使用となると避けられない作業になります。幸いSP-100iのエッジ貼り替えに挑戦される方は少なくないようで、先達の方々が複数ブログに作業内容をアップされてたので、情報収集には困りませんでした。こういう時、ネットは本当にありがたいですね。
アースラインについては、かなり以前、調べたり試したりした事がありました。結果、現在はGNDの全てをアースグラウンドから浮かせています。私の耳では違いを聴き取れなかったことと、ヘタをするとグラウンドループなどによる悪影響が発生する可能性を危惧してのことです。
@ジャイアン さん、ここ久しぶりですね。
最近、ラズパイとDACを結合するGPIOの周りを銅箔テープで覆ってみました。
I2Sがノイズの影響を受けやすいということなので、GPIOの短い部分でもラズパイからのノイズ遮蔽の効果があるのかもしれないということで試してみたわけです。
気分的には良いのですが、効果の程は、私の耳ではよくわかりませんでした。
@パパリウス さん
ちょっと考えてみたのですが、ラズパイとHATの間に、絶縁できるシートかテープで銅箔を包んで、入れてみるというのはどうでしょう。放熱のことも考えて少し浮くように短い脚を付けるというものです。
HAT全体となると、プラケースに入れて銅箔を貼ってしまうという形でしょうか。
当然、自作になるわけですが、難易度はとても低いと思います。これから出かけますので、あとで実験してみます。
@パパリウス さん
横から失礼します。m(_ _)m
昔発売されていたPCIカード同士をシールドする
NO-PCI:シールドボード - 玄人志向 というのがありました。
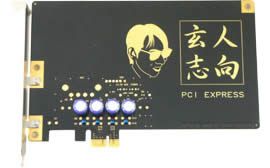
これと同様の考えで間に銅箔基板を挟む形で考えたら良いと思います。
HATの基板外形データーはネット上に転がっているので
どうせ作るならGPIOピン周りはGNDパターンで囲む形にすれば
何か効きそうな気がします。
パパリウスさん 皆様
やっぱりラズパイとHATの干渉を何らかの方法で防いでみたくなりますよね。アイデアとしては、
1.ラズパイ用スタッキングコネクターを使う。
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-10702/
これなら、安心して間に遮蔽板などの工夫ができると思います。
2.GPIO延長ケーブルを使う。
こちらはいろいろな種類がありますが、長さは15㎝MAXで考えた方が良いかもしれません。
当方も現在ラズパイはプラケース入りなので、金属ケースのかっこいいものが欲しいのですが、これはというものは残念ながら見つかっていません。HATを載せたものでも大丈夫な金属ケースがHifiberryなどにあるのですが、見た目イマイチで使う気が起きません。
タカチあたりのアルミケースを使って自作がベストなんでしょうね。
@パパリウス さん
私は、IANさんのところでFifoPiを買ったときにただでもらった、シールド兼ラズパイ電源供給のカードを使っています。
https://github.com/iancanada/DocumentDownload/blob/master/Adapters/ShieldPi/23A.ShieldPi.jpg
これにスタッキングコネクタをハンダ付けしています。
それと、GPIOターミネータを使っています。
https://github.com/iancanada/DocumentDownload/blob/master/Adapters/GPIOterminator/21A.GPIOterminator.jpg
箱は工具が無いのと、板金工作をやったことがないので躊躇しています。